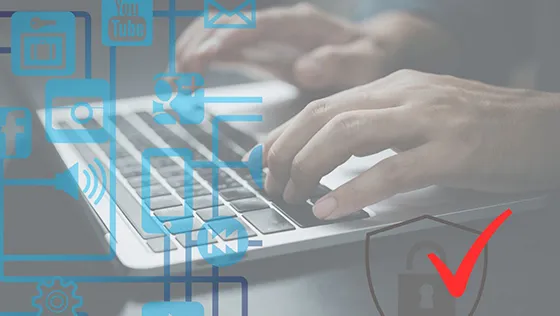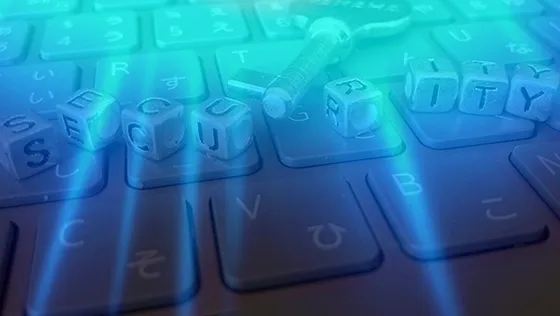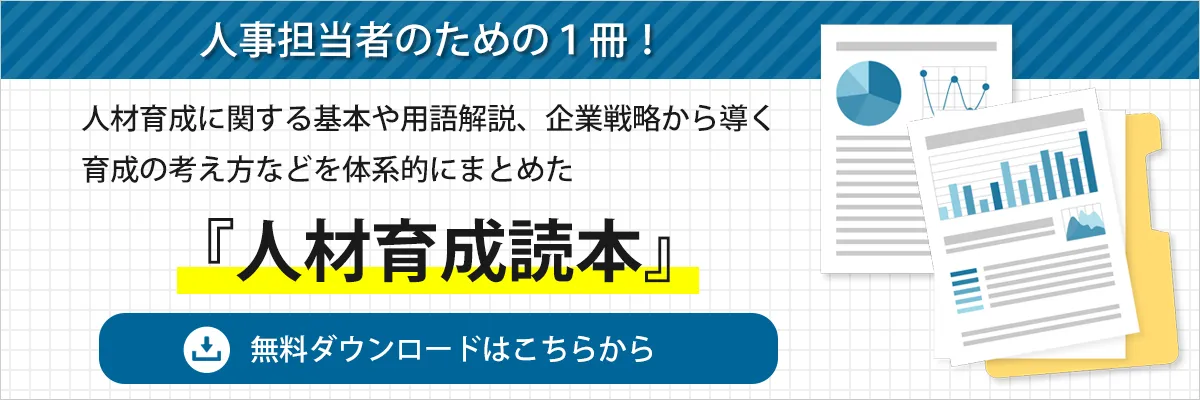情報セキュリティ教育の必要性は?行わない場合のリスクとよくある質問
従業員のセキュリティ意識やリテラシーが低い場合、セキュリティインシデントによって重要な情報資産やビジネスで培ってきた信頼性が損なわれるおそれがあることから、近年は情報セキュリティ教育の必要性がますます高まっています。自社のセキュリティ意識やリテラシーの現状を把握し、従業員に正しい知識を身に着けてもらうための情報セキュリティ教育を行うことによって組織全体の意識向上を図りましょう。
この記事では、情報セキュリティ教育の必要性について解説します。情報セキュリティ教育に取組まない企業が直面するリスクや、具体的な社員教育の進め方などをお伝えするため、ぜひ参考にしてみてください。
情報セキュリティイマジン サービス資料ダウンロード
具体的なケースを通じたテスト形式で「自分ごと」として情報セキュリティリテラシーを高める、オンライン完結で学べるeラーニングです。仮想企業の社員になりきることで、リアルに発生しうるインシデントのケースから、情報セキュリティ意識の重要性と「わかる」と「できる」の違いを理解します。
具体的なケースを通じたテスト形式で「自分ごと」として情報セキュリティリテラシーを高める、オンライン完結で学べるeラーニングです。仮想企業の社員になりきることで、リアルに発生しうるインシデントのケースから、情報セキュリティ意識の重要性と「わかる」と「できる」の違いを理解します。
情報セキュリティ教育とは
「情報セキュリティ教育」とは、情報セキュリティに関する正しい知識を身につけるための社員教育のことです。企業の情報セキュリティ対策の一環として実施されます。教育を通じて従業員のセキュリティ意識やリテラシーを向上させると、セキュリティインシデントの発生防止につながります。近年は、サイバー攻撃や内部要因による機密情報漏えいのリスクを避けるという目的で、多くの企業が情報セキュリティ研修に取組んでいる状況です。
情報セキュリティ教育の必要性
なぜ情報セキュリティ教育の必要性が高まっているのでしょうか。ここでは、情報セキュリティ教育が求められる背景を解説します。
従業員のセキュリティ意識やリテラシーを向上させるため
サイバー攻撃の手口は年々巧妙化・多様化する傾向にあり、危険性が高まっている状況です。そんな中、情報セキュリティ教育を通じて最新の手口を把握することは、被害を未然に防ぐことに役立ちます。さらに、情報セキュリティ教育には内部要因によるセキュリティインシデントを防止する効果も期待できます。従業員の人為的なミスや不注意によって情報漏えいが発生するケースは少なくありません。たとえば「メールの誤送信」「個人情報を含むUSBメモリの紛失」といった事例が挙げられます。情報セキュリティ教育で従業員のセキュリティ意識が向上すれば、一人ひとりの注意力が高まりリスクを軽減することが可能です。
セキュリティインシデント発生時に迅速に対応できるようにするため
情報セキュリティ教育では、セキュリティインシデントを未然に防ぐ対策に加えて、初動対応の方法まで学ぶことができます。万が一トラブルが発生した場合に備えて、原因や影響範囲を迅速に特定し、適切な手順で報告や対処ができる状態をめざします。セキュリティインシデントは完全に防ぐのが難しいため、情報セキュリティ教育で適切な初動対応を学び、被害を最小限に留めることが重要です。
法令を遵守するため
情報セキュリティ教育には従業員のコンプライアンス遵守の意識を高める役割もあります。顧客や取引先からの信頼を得るには、企業活動において法令を遵守することが不可欠です。法的なルールに則って健全な経営を続ける組織は、持続的な成長が期待できます。情報セキュリティ教育を通じて法規制への理解を深めるとともに、法令を徹底して守る意識を高める必要があります。
企業の資産である重要データを保護するため
企業が保有するデータは、経営において重要性の高い資産の一つと見なされ、「情報資産」と呼ばれます。たとえば、「顧客情報」「取引先情報」「製品・サービスの技術情報」「業務のノウハウ」をはじめとした価値あるデータは、社外へ流出しないよう守らなければなりません。情報セキュリティ教育では情報資産の適切な取扱い方を学ぶことができるため、データ保護にも貢献します。
企業の評価や業績に影響を与えるため
万が一、サイバー攻撃や内部要因による情報漏えい事故が発生すると、企業の社会的な信頼性やイメージが著しく損なわれるリスクがあります。さらに、顧客や取引先の情報が流出して第三者に損害を与えた場合には、法的責任を問われたり多額の損害賠償請求を受けたりする可能性があるでしょう。売上の低迷や損失の増加といった経営上の打撃にもつながりかねません。こうしたリスクを避けるためにも、従業員に対する情報セキュリティ教育によって人的対策を徹底する必要があります。
グローバルスタンダードに対応するため
企業の情報セキュリティ対策は、グローバル社会においても重要な経営課題の一つとなっています。海外企業との取引において、情報セキュリティ製品・システムの国際規格「CC(ISO/IEC15408)」、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC27001」の認証取得を求められるケースもあるでしょう。グローバルスタンダードに対応して企業活動を展開するためにも、情報セキュリティ教育への取組みが欠かせません。
情報セキュリティ教育に取組まない場合に起こること
適切な情報セキュリティ教育を実施しない場合、企業はどのようなリスクにさらされる可能性があるのでしょうか。ここでは、情報セキュリティ教育に取組まない企業に起こることを具体的にご紹介します。
セキュリティリスクの増大
情報セキュリティ教育を実施せず、従業員のセキュリティ意識やリテラシーが低い状態のまま放置すると、セキュリティインシデントが発生するリスクが高まります。具体的には、以下のような事態が懸念されます。
- 従業員が機器やソフトウェアのアップデートを行わずに放置して、脆弱性を狙った不正アクセスの被害に遭う
- シャドーIT(=従業員が無断で導入したIT機器やシステム)の脆弱性を狙った不正アクセスや情報漏えい事故が発生する
- 従業員が標的型攻撃メール・サポート詐欺・フィッシングなどの手口で騙されて、社用端末がウイルスやマルウェアに感染する
- 社用端末が不正操作されていることに従業員が気づかない
- セキュリティインシデントが発生しているにもかかわらず、従業員が管理者への報告を行わない
場合によっては、セキュリティインシデントの発見や対処が大幅に遅れて、被害が拡大するおそれがあるため注意が必要です。
経済的な損失
情報セキュリティ教育の不足が原因でセキュリティインシデントが発生すると、企業が経済的な損失を被るおそれがあります。たとえば、個人情報を不適切に取扱って法令に違反した場合、罰金などのペナルティを課される可能性があるでしょう。また、個人情報漏えい事故で損害賠償を行うことになれば、ひとりあたり数千円から数万円の賠償が生じ、場合によっては総額が数億円規模に達するおそれがあります。このほかに、ランサムウェア感染の身代金を誤って支払い、多額の資産を失ってしまうリスクも存在します。
情報セキュリティ教育の進め方
セキュリティインシデントから組織を守るために、情報セキュリティ教育を実施する体制を整備しましょう。ここでは、情報セキュリティ教育の進め方を5つのステップでご紹介します。
Step1.目的の設定
はじめに、情報セキュリティ教育の目的を設定します。自社の目的や情報セキュリティポリシーの内容に沿った学習テーマを検討しましょう。たとえば「業務で頻繁に使うメールを悪用したサイバー攻撃を防ぐ」という目的であれば、「メールを悪用した最新のサイバー攻撃の手口と対策方法」といった教育内容が考えられます。
Step2.対象者の選定
続いて、情報セキュリティ研修の対象者を選定します。一般的に、情報セキュリティ研修は全従業員を対象として、定期的に実施するケースが多いといえます。一方、場合によっては新入社員・中途社員の入社直後に実施するケースもあるため、自社の状況に応じて検討しましょう。
Step3.実施時期や頻度の決定
同様に、情報セキュリティ研修の実施時期や頻度を定めます。全従業員を対象とした定期的な情報セキュリティ研修は、「年に1回」「半期に1回」といったタイミングで行うとよいでしょう。また、自社の情報セキュリティポリシーや社内ルールを変更したタイミングに合わせて実施することも大切です。
Step4.実施方法の選定
情報セキュリティ研修の実施方法には、インターネットを介して受講する「eラーニング」や、研修会場で講師から対面で講義を受ける「集合研修」などの種類があります。また、研修コンテンツを社内で内製する方法と、外部の企業が提供する研修コンテンツを利用する方法があります。なかでも、情報セキュリティ教育に特化した外部のeラーニングコンテンツを活用すると、最新情報を網羅した高品質な研修を実施できる点がメリットです。
Step5.効果測定とフォローアップの実施
情報セキュリティ研修の実施後は、効果測定やフォローアップを実施して、知識の定着化や研修プログラムの改善を図ります。受講後の理解度テストやアンケートを通じて受講者の状況を把握し、必要に応じて学習のサポートを行いましょう。
情報セキュリティイマジン
具体的なケースを通じたテスト形式で「自分ごと」として情報セキュリティリテラシーを高める、オンライン完結で学べるeラーニングです。仮想企業の社員になりきることで、リアルに発生しうるインシデントのケースから、情報セキュリティ意識の重要性と「わかる」と「できる」の違いを理解します。
具体的なケースを通じたテスト形式で「自分ごと」として情報セキュリティリテラシーを高める、オンライン完結で学べるeラーニングコンテンツです。情報セキュリティ意識の重要性と「わかる」と「できる」の違いを理解します。
情報セキュリティ教育以外に行うべきセキュリティ対策
情報セキュリティ教育による従業員のリテラシー向上は、セキュリティ対策の中でも「人的対策」に該当します。セキュリティを向上させるには、このほかにも「技術的対策」や「物理的対策」を講じることが大切です。ここでは、企業が実施すべき技術的・物理的なセキュリティ対策についてご紹介します。
不正を監視するツールの導入
PCやスマートフォンなどの社用端末を適切に管理するために、ログ監視ツールを導入しましょう。ログ監視ツールを利用すると、端末の異常を24時間体制で監視して即座に検知できるので、不正な操作や情報漏えいといったトラブルを早期に発見するために役立ちます。また、万が一セキュリティインシデントが発生した際に、原因を速やかに特定して対策を講じることが可能です。
セキュリティソフトウェアの導入
社内の端末やネットワークにセキュリティソフトを導入して、幅広いサイバー攻撃の手口に備えましょう。セキュリティソフトには、ウイルス・マルウェア・フィッシング・迷惑メールをはじめとした多様なサイバー攻撃に対応し、端末やネットワークを保護する機能が搭載されています。導入することで、外部要因で発生するセキュリティインシデントを防止するための基本的な対策を実施できます。
多要素認証の導入
多要素認証とは、2つ以上の要素を組み合わせて認証を行うことで、セキュリティを強化する方法です。パスワードや暗証番号などの「知識情報」、端末やICカードなどの「所持情報」、指紋・顔・静脈などの「生体情報」のうち複数を組み合わせます。社内のシステムやネットワークにログインする際に多要素認証を導入すると、セキュリティの強度を高めることが可能です。
データのバックアップ
セキュリティ対策やBCP(事業継続計画)の観点から、定期的に社内の重要なデータのバックアップを取っておくのが望ましいといえます。バックアップを取ることで、サイバー攻撃や大規模災害でデータに被害が及んだ場合に、迅速に復旧して業務を継続しやすくなります。その際は、バックアップの対象・方法・頻度などをルールとして定めるとともに、情報セキュリティポリシーに明記しておくとよいでしょう。
機器の持ち出し制限
社用端末・USBメモリ・外付けHDDなどの機器は、セキュリティの観点から社外への持ち出しに制限をかけることが重要です。テレワークや出張で社外へ持ち出す必要がある場面では、社内ルールに則って手続きを行うとともに、第三者への貸与や公共のWi-Fiへの接続を禁止する必要があります。同様に、無断での私物機器の社内持ち込みや、社内LANへの接続を禁止することも大切です。
情報セキュリティ教育の必要性に関するよくある質問
ここでは、情報セキュリティ教育の必要性に関するよくある質問と、その回答をご紹介します。改めて基本的な知識を確認してみましょう。
無料で使える情報セキュリティ教育用の教材はある?
インターネット上には、企業の情報セキュリティ教育に役立つ無料の教材やサイトが公開されています。
たとえば、国家サイバー統括室(NCO)が提供する資料「インターネットの安全・安心ハンドブック」や、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が提供する資料「5分でできる!情報セキュリティポイント学習」は、研修コンテンツとして活用できます。
【参考】「インターネットの安全・安心ハンドブック」(NCO) https://security-portal.nisc.go.jp/guidance/handbook.html
【参考】「5分でできる!情報セキュリティポイント学習」(IPA) https://www.ipa.go.jp/security/sec-tools/5mins_point.html
また、IPAが運営する「ここからセキュリティ!情報セキュリティ・ポータルサイト」、総務省が運営する「国民のためのサイバーセキュリティサイト」には、情報セキュリティの基礎知識を無料で学習できる内容が充実しています。
【参考】「ここからセキュリティ!情報セキュリティ・ポータルサイト」(IPA) https://www.ipa.go.jp/security/kokokara/
【参考】「国民のためのサイバーセキュリティサイト」(総務省) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/
情報セキュリティに関する法律は?
情報セキュリティに関連する法律の例として「サイバーセキュリティ基本法」「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」などが挙げられます。これらの法律は、インターネットを利用した不正行為の防止を目的として定められています。
【参考】「サイバーセキュリティ関連の法律・ガイドライン」(総務省) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/basic/legal/
情報セキュリティ教育ベンダーの選び方は?
外部の研修サービスを利用する場合は、以下の5つのポイントに着目して情報セキュリティ教育ベンダーを選びましょう。
- 従業員が受講しやすい研修形態か
- 情報セキュリティの最新情報が網羅されているか
- 従業員が“自分ごと”として学習できるか
- 受講者のモチベーションを維持する仕組みがあるか
- 管理機能やフォロー体制が充実しているか
社内のセキュリティ意識やリテラシーの向上に貢献する、効果的な研修を実施できるベンダーを選ぶことが大切です。
情報セキュリティ教育の必要性を感じたらNTT HumanEXにお任せください
ここまで、情報セキュリティ教育の必要性、教育に取組まない企業が直面するリスク、社員教育の進め方などをお伝えしました。社員教育によって従業員のセキュリティ意識やリテラシーを高めると、セキュリティインシデントの防止につながります。情報セキュリティ教育の必要性を感じたら、NTT HumanEXのeラーニングコンテンツ「情報セキュリティイマジン」がおすすめです。
「情報セキュリティイマジン」では、日常業務で起こり得るセキュリティリスクをリアルに体感しながら、“自分ごと”として学ぶことができます。身近な事例を題材に、従業員自身が「自分ならばどうすべきか」を想像しながら学びを深める設計となっています。IPAの「情報セキュリティ10大脅威」を網羅したコンテンツで、最新のサイバー攻撃の手口に備えることが可能です。情報セキュリティ担当者の方は、お気軽にお問い合わせください。
情報セキュリティイマジンに関するお問い合わせ
具体的なケースを通じたテスト形式で「自分ごと」として情報セキュリティリテラシーを高める、オンライン完結で学べるeラーニングです。仮想企業の社員になりきることで、リアルに発生しうるインシデントのケースから、情報セキュリティ意識の重要性と「わかる」と「できる」の違いを理解します。
具体的なケースを通じたテスト形式で「自分ごと」として情報セキュリティリテラシーを高める、オンライン完結で学べるeラーニングです。仮想企業の社員になりきることで、リアルに発生しうるインシデントのケースから、情報セキュリティ意識の重要性と「わかる」と「できる」の違いを理解します。