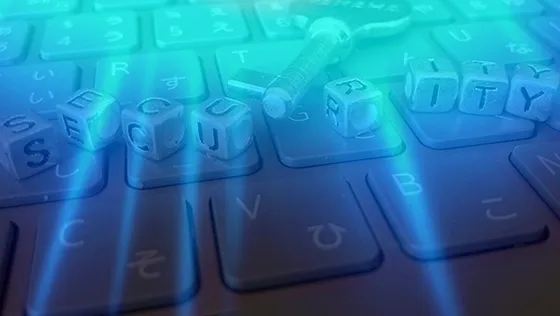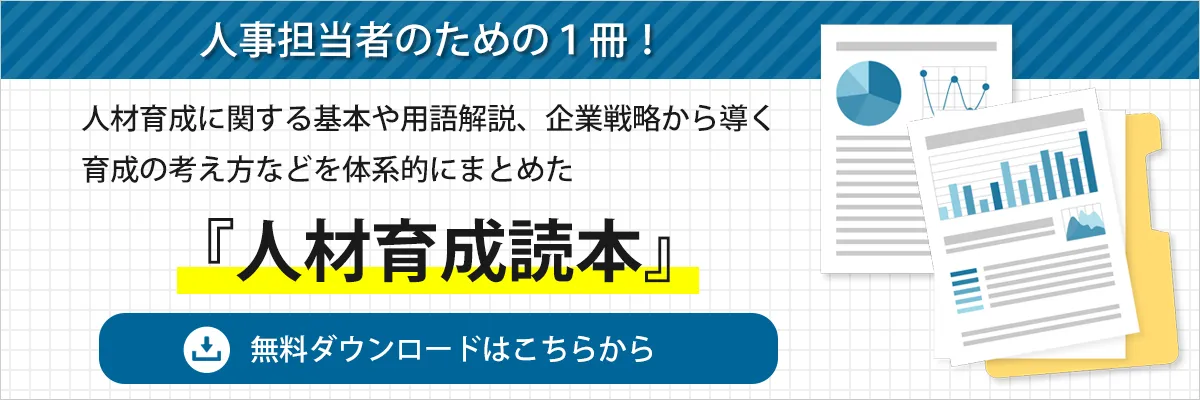企業向けの情報セキュリティ研修資料10選!研修を行う流れと課題も解説
近年は企業を狙ったサイバー攻撃が増加するとともに、手口がますます巧妙化することから、あらゆる日常業務にセキュリティリスクが潜んでいるといえます。自社の情報資産をサイバー攻撃から守るためには、一人ひとりの従業員が当事者意識を持って対策できるよう、情報セキュリティ研修で啓発を続けていくことが大切です。
そこでこの記事では、情報セキュリティの研修資料を作成する際に役立つ資料・Webサイト10選をご紹介します。また、企業の情報セキュリティ対策に特化した実践的な動画コンテンツもご紹介するため、担当者の方はぜひ参考にお読みください。
情報セキュリティイマジン サービス資料ダウンロード
具体的なケースを通じたテスト形式で「自分ごと」として情報セキュリティリテラシーを高める、オンライン完結で学べるeラーニングです。仮想企業の社員になりきることで、リアルに発生しうるインシデントのケースから、情報セキュリティ意識の重要性と「わかる」と「できる」の違いを理解します。
具体的なケースを通じたテスト形式で「自分ごと」として情報セキュリティリテラシーを高める、オンライン完結で学べるeラーニングです。仮想企業の社員になりきることで、リアルに発生しうるインシデントのケースから、情報セキュリティ意識の重要性と「わかる」と「できる」の違いを理解します。
情報セキュリティ教育の基礎知識
はじめに、情報セキュリティ教育の概要や、企業における情報セキュリティ教育の重要性について解説します。研修資料作成へ向けて、基礎知識を押さえておきましょう。
情報セキュリティ教育とは?
情報セキュリティ教育とは、情報セキュリティ事故を未然に防いだり、事故のリスクを軽減したりするための教育を指します。従業員が情報セキュリティに関する知識やスキルを習得し、日常業務を安全に運営する目的で実施します。近年は企業を狙ったサイバー攻撃が増加し、手口が巧妙化している状況です。不正アクセスやマルウェア感染により、情報漏えいや金銭被害などが懸念され、情報セキュリティ教育の重要性がますます高まっています。
情報セキュリティが重要な理由
万が一情報セキュリティ事故が発生すると、企業活動に甚大な影響がもたらされるため、日頃から組織的に対策を講じなければなりません。たとえば、サイバー攻撃によって顧客や取引先の情報が漏えいすると、企業の信頼性やイメージが損なわれ、経営上の打撃を受ける可能性があるでしょう。場合によっては、大幅な売上の減少や損害賠償など、企業の存続にかかわる事態に発展するおそれがあります。
また、情報セキュリティ対策は世界的に重要な経営課題と見なされており、ビジネスシーンでは企業の意識向上が求められています。セキュリティ面での信頼性を確保するために、国際標準として規格化された「情報セキュリティ製品・システム評価基準(ISO/IEC15408)」「情報セキュリティマネジメントシステムの認証基準(ISO/IEC27001)」などの認証を受ける企業が多くなっています。認証を受けると、一定のセキュリティ基準を満たしている事実を客観的に証明することが可能です。
情報セキュリティ教育の研修資料として利用できる資料・Webサイト10選
情報セキュリティ教育で用いる研修資料を作成する際は、以下のWebサイトを活用するのがおすすめです。企業の情報セキュリティ担当者の方は、ぜひ支援サイトの公開資料を社員教育にお役立てください。
情報セキュリティ10大脅威2025
「情報セキュリティ10大脅威2025」は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)がオンラインで無料公開している資料です。例年、IPAが最新の脅威の中から社会的な影響が大きい事案を選出し、攻撃手口・具体的な事例・対策方法などを紹介しています。企業が脅威の傾向を把握し、自社に必要な対策の立案に役立てることが目的です。資料は組織向けと一般向けに分かれているため、情報セキュリティ教育では業務に即した「組織編」を活用するとよいでしょう。
なお、2025年の組織における情報セキュリティ10大脅威として、以下の事案が掲載されています。
情報セキュリティ10大脅威2025(組織)
- ランサム攻撃による被害
- サプライチェーンや委託先を狙った攻撃
- システムの脆弱性を突いた攻撃
- 内部不正による情報漏えい等
- 機密情報等を狙った標的型攻撃
- リモートワーク等の環境や仕組みを狙った攻撃
- 地政学的リスクに起因するサイバー攻撃
- 分散型サービス妨害攻撃(DDoS攻撃)
- ビジネスメール詐欺
- 不注意による情報漏えい等
【出典】「情報セキュリティ10大脅威 2025」(独立行政法人情報処理推進機構) https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2025.html
インターネットの安全・安心ハンドブック
「インターネットの安全・安心ハンドブック」は、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が無料公開しているハンドブック型の資料です。サイバー攻撃の手口やサイバーセキュリティ対策の基本など、基礎知識を体系的に学べる内容となっています。中小企業・小規模事業者向けのデジタルブックや電子書籍ファイルが配布され、社内体制の整備はもちろん、情報セキュリティ教育にも活用しやすくなっています。2025年3月にVer5.10へ改訂されました。
【出典】「インターネットの安全・安心ハンドブック」(内閣サイバーセキュリティセンター) https://security-portal.nisc.go.jp/guidance/handbook.html
5分でできる!情報セキュリティポイント学習
「5分でできる!情報セキュリティポイント学習」は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が無料公開している情報セキュリティ教育向けの学習コンテンツです。学習コースの種類としては、「経営者・管理者向けコース」「従業員向けコース」「自社診断シート25問に対応した学習コース」「情報セキュリティ5か条対応コース」「学校指導者向けコース」が用意されています。また、各コースは複数のテーマから構成されていて、1テーマあたり5分程度で学んだうえで、確認テストによる理解度チェックが可能です。
【出典】「5分でできる!情報セキュリティポイント学習」(独立行政法人情報処理推進機構) https://www.ipa.go.jp/security/sec-tools/5mins_point.html
セキュリティインシデント対応机上演習教材
「セキュリティインシデント対応机上演習教材」は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が無料公開している情報セキュリティ教育向けの教材です。座学形式での研修に適したPowerPointファイルが提供されています。セキュリティインシデントの発生を想定して、被害を最小限に留めるための適切な対応方法を学べる研修内容となっています。教材を用いながらグループディスカッションや発表を行い、セキュリティインシデント対応への理解を深めることが可能です。
【出典】「セキュリティインシデント対応机上演習教材」(独立行政法人情報処理推進機構) https://www.ipa.go.jp/security/sec-tools/ttx.html
一般初心者向け情報セキュリティ教材
「一般初心者向け情報セキュリティ教材」は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が無料公開しているIT初心者向けの教材です。PCやスマートフォンを使い始めて間もない方でも理解できるよう、平易な言葉遣いとイラストによってわかりやすく解説されていることが特徴です。なかでも情報セキュリティ対策の教材は、「1.コンピュータウイルス」「2.ネット詐欺」「3.パスワード」「4.外出先での利用」「5.物理的なセキュリティ対策」のテーマで構成されています。
【出典】「一般初心者向け情報セキュリティ教材」(独立行政法人情報処理推進機構) https://www.ipa.go.jp/security/sec-tools/general_security_materials.html
中小企業向け情報セキュリティ対策
「中小企業向け情報セキュリティ対策」は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が中小企業・小規模事業者向けに公開しているポータルサイトです。関連サイトの中から自社の情報セキュリティ教育に最適な資料を探せます。たとえば、中小企業が情報セキュリティ対策を自己宣言する制度「SECURITY ACTION」のサイトや、関連企業を巻き込んだサプライチェーン攻撃に備える「サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム(SC3)」のサイトが掲載されています。
【出典】「中小企業向け情報セキュリティ対策」(独立行政法人情報処理推進機構) https://www.ipa.go.jp/security/sme/list.html
映像で知る情報セキュリティ
「映像で知る情報セキュリティ」は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が無料公開している情報セキュリティ教育向けの映像コンテンツです。情報セキュリティの脅威や対策について学べる数十秒~約10分の短い動画が充実しています。テーマのジャンルは「情報セキュリティ対策の基本」「サイバー攻撃」「テレワークのセキュリティ」「内部不正、情報漏えい対策」「新入社員向け」「SNSの心得」といった幅広い領域がカバーされています。
【出典】「映像で知る情報セキュリティ」(独立行政法人情報処理推進機構) https://www.ipa.go.jp/security/videos/index.html
テレワークにおけるセキュリティ確保
「テレワークにおけるセキュリティ確保」は、テレワーク体制のセキュリティ確保を目的として総務省が公表する資料集です。資料は大きく「テレワークセキュリティガイドライン」と「中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き(チェックリスト)」に分かれています。テレワーク実施企業の安全な運用に役立てるとともに、従業員向けのハンドブックを情報セキュリティ教育に活用することが可能です。ハンドブックは印刷して従業員に配布し、携行できる形式となっています。
【出典】「テレワークにおけるセキュリティ確保」(総務省) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/
「基本編:個人情報管理の重要性」「基本編:個人情報の取扱いに関する事故を起こさないために(各編)」
プライバシーマーク制度の運用を担う一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が無料公開している、個人情報の取り扱いに関する社内教育用参考資料です。業務で個人情報を取り扱う企業に求められる運用ルールや管理方法、近年の情報漏えい事故の傾向、事故防止へ向けた対策方法などが解説されています。企業の日常業務やテレワークにおいて注意すべき点が具体的な事例とともに紹介されており、実務担当者や管理職の研修に活用できます。
【出典】「基本編:個人情報管理の重要性」「基本編:個人情報の取扱いに関する事故を起こさないために(各編)」(一般財団法人日本情報経済社会推進協会) https://privacymark.jp/guideline/wakaru/index.html#tools
迷惑メール対策BOOK『撃退!迷惑メール』
「迷惑メール対策BOOK『撃退!迷惑メール』」は、一般社団法人日本データ通信協会が無料公開しているハンドブック型の資料です。最新の迷惑メールの手口が取り上げられています。たとえば2025年度版では、有名企業やブランドになりすましたフィッシング詐欺、大手ECサイトや宅配便業者になりすました偽メールなどの事例が紹介されています。企業を狙って送信される迷惑メールの手口を把握し、ゼロトラスト(=信頼しないことを前提としたセキュリティ対策の考え方)の基本を学ぶことが可能です。
【出典】「迷惑メール対策BOOK『撃退!迷惑メール』」(一般社団法人日本データ通信協会) https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/info/pamphlet_gm.html
5分でできる!情報セキュリティ自社診断
「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が提供する情報セキュリティの診断ツールです。25個の診断項目に沿って回答することで、最低限の情報セキュリティ対策を実施できているか、自社で診断できるようになっています。情報セキュリティ教育に取り入れることで、受講者の情報セキュリティ意識をチェックするとともに、解説編を参考にしながら自社に不足している対策を強化することが可能です。
【出典】「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」(独立行政法人情報処理推進機構) https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/5minutes.html
効果的な情報セキュリティ教育を行う流れ
年々増加するサイバー攻撃に対して従業員の当事者意識を高めるには、情報セキュリティ教育が不可欠です。自社の情報資産を守るために、以下の5つのステップで研修を導入し、効果的な情報セキュリティ教育を実施しましょう。
情報セキュリティイマジン
具体的なケースを通じたテスト形式で「自分ごと」として情報セキュリティリテラシーを高める、オンライン完結で学べるeラーニングです。仮想企業の社員になりきることで、リアルに発生しうるインシデントのケースから、情報セキュリティ意識の重要性と「わかる」と「できる」の違いを理解します。
具体的なケースを通じたテスト形式で「自分ごと」として情報セキュリティリテラシーを高める、オンライン完結で学べるeラーニングコンテンツです。情報セキュリティ意識の重要性と「わかる」と「できる」の違いを理解します。
Step1.テーマを決める
まずは、自社の情報セキュリティ教育の目的を明確にしたうえで、研修のテーマを設定します。従業員に習得させるべき知識やスキルを具体的に洗い出しましょう。たとえば、日常業務で顧客の個人情報を取り扱う場合は「機密情報・個人情報の取り扱い方」などのテーマ、テレワーク実施企業では「テレワーク勤務者が守るべきルール」などのテーマが適しています。
Step2.対象者を決める
続いて、情報セキュリティ教育の対象者を設定します。全従業員を対象とするケースのほかに、特定の業務に携わる従業員を対象とするケース、管理職や新入社員を対象とするケースなどが挙げられます。その際は、対象者が担当する業務内容や階層によって受講すべき研修のレベルや学習内容が異なる点に留意しましょう。
Step3.実施頻度・時期を決める
組織の状況や必要性に応じて、対象者に情報セキュリティ教育を実施する時期や頻度を設定し、社員教育の計画を立てます。従業員がコア業務の合間に無理なく実施できるよう配慮しましょう。たとえば、新入社員や中途社員が入社したタイミングで実施するほか、数カ月~半年に1回のタイミング、1年に1回のタイミングで定期的に実施する方法があります。
Step4.実施方法を決める
情報セキュリティ教育の実施方法には、主に「社内研修」「外部講師によるセミナー」「eラーニング」などの選択肢があります。自社に適した実施方法を検討しましょう。近年はオンラインで受講できるeラーニングを活用する企業が多くなっています。eラーニングはシステム上で進捗状況や理解度を管理できる点や、対象者が都合に合わせて柔軟に受講できる点がメリットです。状況に応じて、eラーニングと集合研修の併用も有効です。
Step5.効果測定を行う
情報セキュリティ教育の実施後は、定期的に効果測定を行って教育の成果を確認します。理解度テストを実施して一人ひとりの知識やスキルの習得状況をチェックしましょう。理解度が低い従業員には、再受講を促すほか、教育の実施方法や頻度を見直すことが大切です。研修実施後のフォローアップによって、知識やスキルの定着を図りましょう。
情報セキュリティ教育における課題
情報セキュリティ教育を実施したものの、従業員に対して意識の変容を起こせず、セキュリティ意識が低いままとなってしまうケースが少なくありません。この場合に原因として考えられるのは、研修での学びを「自分ごと」として捉えられないことです。「他人ごと」の認識で研修を受講しても、日常業務にかかわる重要な学習であるという自覚が芽生えなかったり、身の回りにあるリスクに気づけなかったりするおそれがあります。
こうした事態を避けるためにも、情報セキュリティ教育を実施するときは、自分ごと化を促せる研修資料や教材を選ぶことが重要です。セキュリティインシデントを「自分ごと」として捉えるには、実際の業務で起こり得る身近な事例をもとに作られたコンテンツや、受講者自身に考えさせるよう設計されたコンテンツが適しています。研修の実施そのものが目的とならないよう、従業員のセキュリティ意識向上を目指して研修を実施しましょう。
情報セキュリティ研修資料に適した「情報セキュリティイマジン」
ここまで、企業の情報セキュリティ教育の基礎知識や、研修資料を作成する際に役立つ資料・Webサイト10選、効果的な情報セキュリティ教育を行う流れなどを解説しました。
情報セキュリティ教育のために従業員の自分ごと化を促す研修資料や教材をお探しなら、NTT HumanEXの「情報セキュリティイマジン」をおすすめします。現場で役立つ実践的な内容と、受講者自身に想像させて学習を深める設計によって、「自分ごと」として学べる動画コンテンツとなっています。IPAの「情報セキュリティ10大脅威」を網羅しているため、最新のサイバー攻撃の手口に備えた対策が可能です。
「情報セキュリティイマジン」について詳しくは、以下のページからご覧いただけます。どうぞお気軽にお問い合わせや資料請求をご利用ください。
情報セキュリティイマジンに関するお問い合わせ
具体的なケースを通じたテスト形式で「自分ごと」として情報セキュリティリテラシーを高める、オンライン完結で学べるeラーニングです。仮想企業の社員になりきることで、リアルに発生しうるインシデントのケースから、情報セキュリティ意識の重要性と「わかる」と「できる」の違いを理解します。
具体的なケースを通じたテスト形式で「自分ごと」として情報セキュリティリテラシーを高める、オンライン完結で学べるeラーニングです。仮想企業の社員になりきることで、リアルに発生しうるインシデントのケースから、情報セキュリティ意識の重要性と「わかる」と「できる」の違いを理解します。